記事作成:2025年2月24日(月)
ひな祭り まるわかり!
最初に、本記事は神楽の先生、加藤俊彦先生に教えていただいた内容をもとに、以下の本も参考にして作成した記事となります。
・京の儀式作法書(著:岩上力先生)
・京のならわし(著:岩上力先生)
加藤先生による解説動画版はこちら!

目次
桃の節句とは
まず、桃の節句(もものせっく)とは、3月3日!とは限らない時代もありました。(ええ!?)
桃の節句とは、この節句とありますように、五節句のうちの1つです。
節句は、神様にお供物をして、けがれをはらっていただくタイミングです。
<参考>初節句は七草粥!節句についても説明
桃の節句は本来、3月の最初の巳の日になります。蛇とのかかわりも大事な巳の日ですね。
<参考>巳の日についてはこちら
ですので、その年の巳の日によっては3月3日ではない日になっていました。ただ、江戸時代からは、3月3日が桃の節句と固定されたそうです。
ちなみに、桃は魔除けとされているってご存知でしたか?

実際に、日本の神話で、イザナギ・イザナミの神様のお話しの中で、桃を投げて追いかけてくる悪いものを退けたというお話しがあるように、桃は魔除けと信じられています。
ですので、この穢れを祓う時期にはぴったりですよね。
雛人形・ひな祭りの由来
最初に、節句の意味に戻ります。けがれを祓うべきタイミングになります。
古代中国ではこの日に水辺で体を清めていたそうで、これが日本に伝わりました。
まず、和紙で形代(かたしろ)を作ります。これを人形(ひとがた)といいます。
そして、人形で体をなでてけがれをうつして川に流しました。平安時代からといわれています。これが、流し雛(ながしびな)につながったそうです。
<参考>人形といえば大祓(おおはらえ)
また、一方で平安時代の貴族の間では”ひいな遊び”という人形をかわいがるものがありました。今で言う、人形の着せ替え遊びのようなものだったそうです。
この2つ、人形と”ひいな遊び”が合体して、現代の”雛人形”もとい”ひな祭り”が出来上がったそうです。
雛人形の並べ方
一番上が、左が男雛、右が女雛が一般的ですが、京都では逆にします。これは、御所の紫宸殿からみた左と右にならってですが、加藤先生いわく、明治時代までは逆だったそうです。西洋に倣っていまの左が男雛、右が女雛になったそうですよ。
あとは、基本シンプルに右側に年上の方を置く!(加藤先生直伝)
ちなみに、仕丁(しちょう)さんと呼ばれる3人組は面白く、怒り、泣き、笑いの表情から三人上戸と呼ばれています。こちらも、一番年をとっている方が右です。
そして、五人囃子(ごにんばやし)については、左から右にいくにつれ、だんだん上にいくとのことで、確かにと思いました!
「太鼓」「大皮」「小鼓」「笛」「謡(うたい)」
早く片付けないと婚期が遅れる?
さて、雛人形は早く片付けないと婚期が遅れる・・という話しがあります。が、岩上先生いわく、迷信のようです。
ただし、しつけとして、「いつまでも出しておくのはだらしがないよ!」という意味で伝わった可能性は多いにあり、先ほどもあったようにけがれをうつして流すものでしたので早くしまうにこしたことはないだろうとのことでした。
人形の歴史を鑑みるに、おっしゃる通りだなと思いました。が、、遅れた・・どうしよう・・と思い悩んでいる方には朗報ですね!
ひな祭りの豆知識
ちなみに、雛人形を買う時、みなさんは何を基準に買い求められますか?
岩上先生いわく、「顔で選ぶなら、右大臣が好みかを見た方がよいですよ」とのことでした!ぜひ、みなさん、雛人形を買う時は右大臣が好みかを注意してみてみましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?なかなか深いひな祭りでした!いろいろとご存知なかったこともあったかと思います。
でも、加藤先生からとても大切な言葉をいただいています!

まさにそうだと思います!なぜかは知りつつも、自分として楽しみたい方法で、ぜひ楽しんでいただけましたら幸いです!

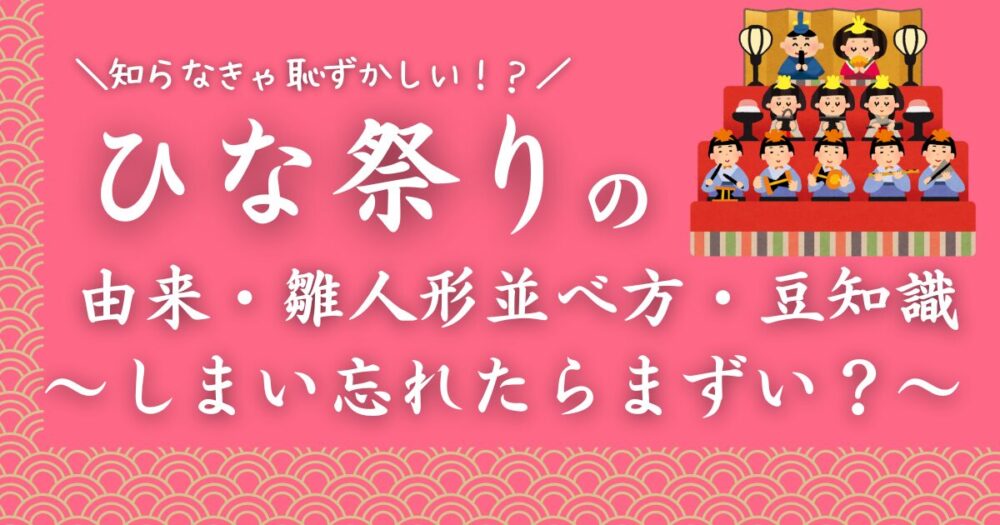

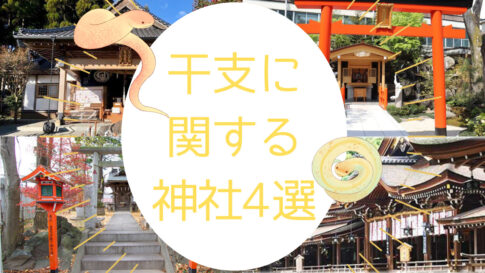

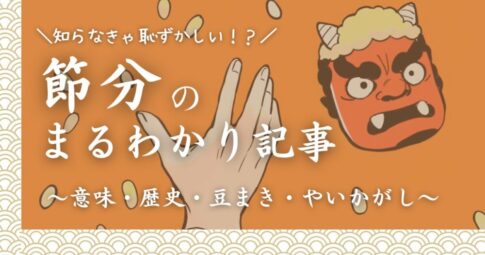
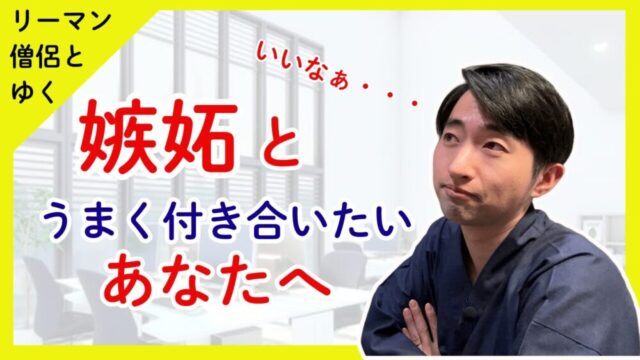


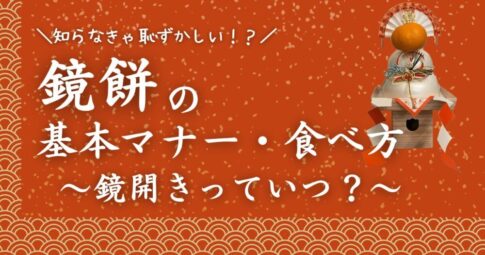
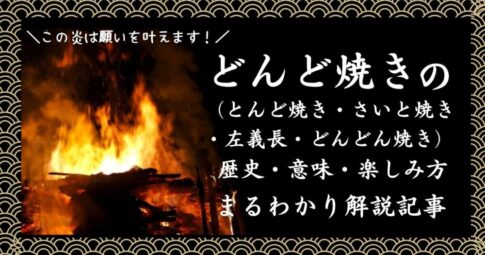


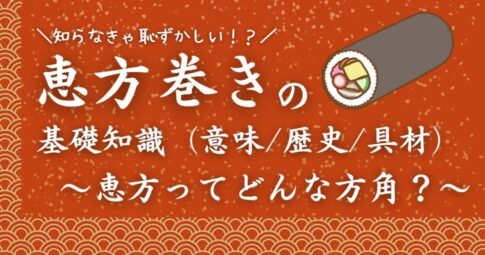



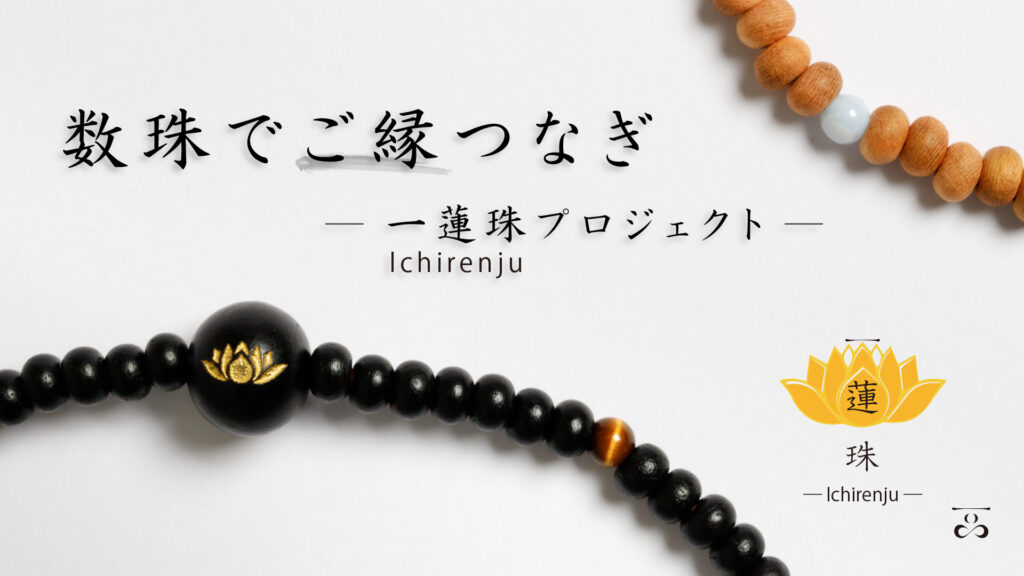


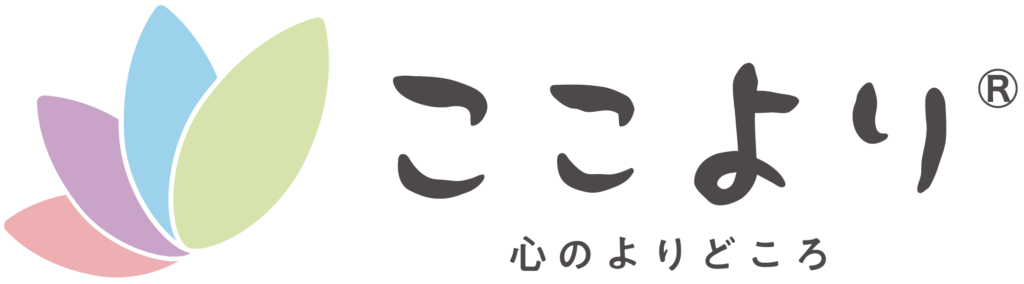
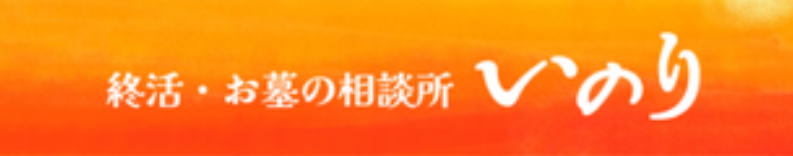


本記事では、ひな祭りについてその由来、桃の節句、雛人形の並べ方、ひな祭りの楽しみ方などをわかりやすく解説しています!