記事更新:2025年1月29日(水)
本記事では、大原問答のお寺、勝林院(京都 大原)天野さんにご取材した内容をまとめております。
今回の記事内容はこちらの動画内容をもとにしたものとなっております。
目次
・アクセス
お寺の歴史
伝説的なところとしては、慈覚大師円人様によって創建されたと言われているものの、それを示す文献などはないそうです。
そして、文献で確認できる最古としては、1013年に寂源によって声明による念仏修行の道場として創建されました。
次に、約90年のちに来迎院が創建されると、二つの本堂を中心として僧坊が建立され、多くの僧侶が声明の研究研鑽をする拠点となりました。
ちなみに、法然上人の大原問答で有名です。
魚山大原寺とは
こうして、勝林院と来迎院を中心とした大原東部の寺院群は、魚山大原寺と総称されるようになられます。
このお寺様は、火災で2度、水害で1度全損をしながら再建されてきたそうでして、本当に災害と戦ってこられたお寺様です。
そして、現在のお寺のお堂は1778年に再建されたものです。幅七間・奥行六間の総欅造りで屋根は木の板を重ねて葺いた杮葺です。欄間や蛙股などに彫り込まれた立体的な彫刻は当時の木彫技術の素晴らしさを今に伝えています。
境内の小川の意味合い
元々、小川が流れていたというのはあるかと思います。
ただ、この小川は大原の信仰では三途の川を表しています。
小川を渡ってお寺のお堂の側はまさに極楽浄土を表すわけです。
此岸(この世)と彼岸(あの世)を分けているわけですね。
仏像から出る綱の意味
五色の綱と、白い、白布の綱がある。
白い綱の方は、葬送の儀礼で使われるものです。
大原の里墓は、勝林院裏手の谷の方にあります。そこに葬列が向かっていくときに先ほどの小川の向こう側(此岸:この世)に祭壇を設けて、角塔婆を建てます。
そして、故人の手と白い綱(阿弥陀様の手)をつないで、念仏を申してお墓に向かっていきます。
五色の綱は、生きているうちに阿弥陀さんとご縁を結べるようにというためで後からできました!
仏像について
大原大仏とも呼ばれます、丈六の仏様です。
勝林院さん・往生極楽院さん・浄蓮華院さんの3大仏が大原さんに当時はありました。今は、勝林院と往生極楽院のみです。
声明ボタンがある
声明が聞けるボタンがあります!たくさんの種類の声明がアラカルトのように聞けます!おすすめですよ。
アクセス
<バス>
JR京都駅・京阪三条駅・地下鉄国際会館駅から 京都バス「大原行」で終点「大原」バス停より 徒歩10分
<車>
国道367号線大原三千院周辺の民間駐車場に駐車
徒歩10分






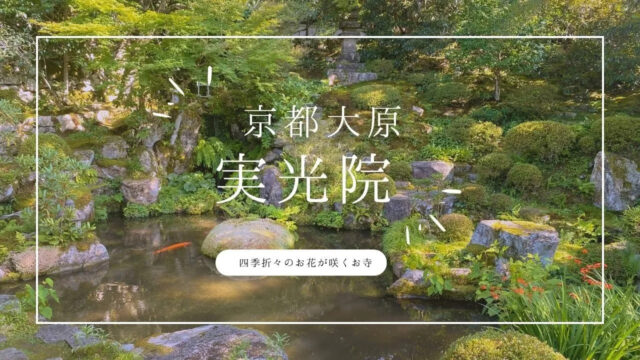









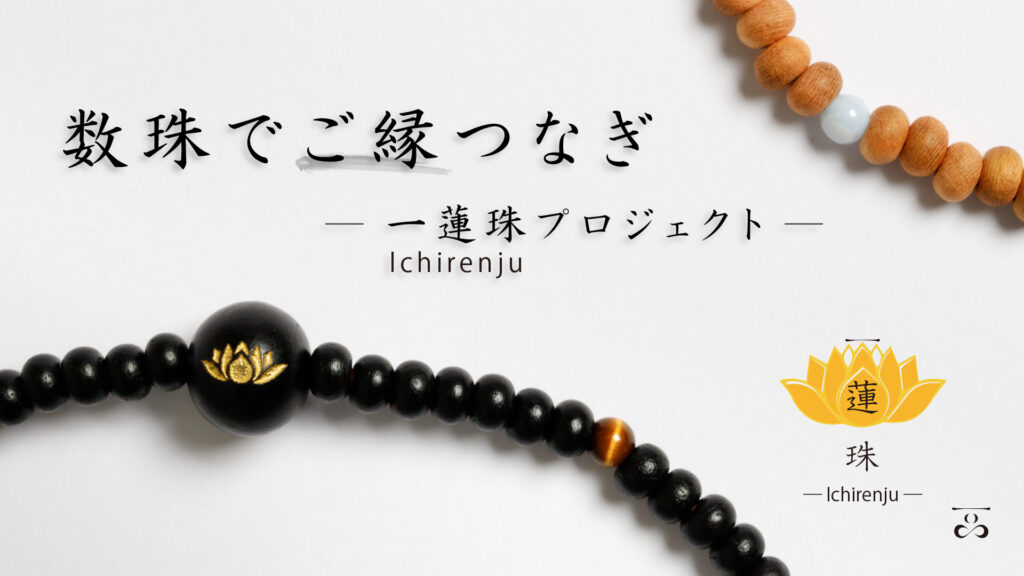


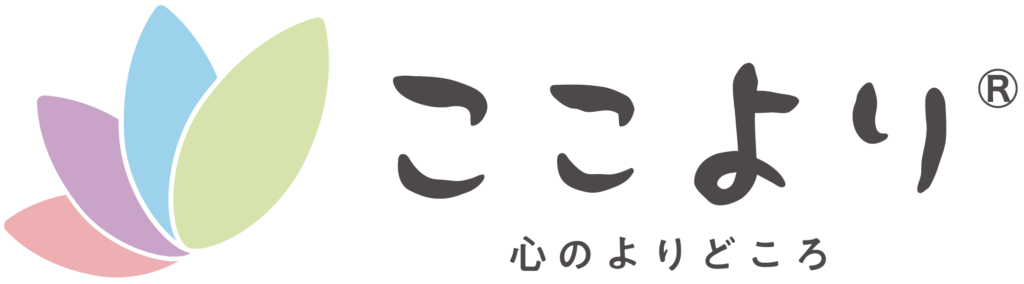
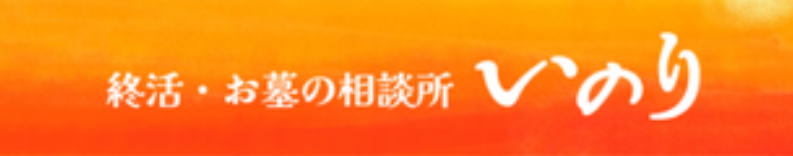


眼に見える形で阿弥陀様とご縁を結べるというのは、何よりも救いになりますね。