作成日:2025年8月14日
目次
- 共通の風習
- 青森県
- 東京都
- 京都府
- 徳島県
- 長崎県
- 沖縄県
共通の風習
最初にお盆って何?って思いますよね、お盆とは、家族や親族が集まってご先祖様や故人を偲び供養する行事だそうです。
- 精霊馬:きゅうりとなすでできた供物。御先祖様の霊が乗って現世に帰ってこれるように、きゅうりを馬に、なすを牛に見立ています。なぜ馬と牛なのかというと、「馬に乗って早く帰ってきて、牛に乗ってゆっくり帰れるように」という願いが込められている説が有力です
- 盆提灯:御先祖様の霊が自分の家の場所を迷わないようにするための灯です。新盆では白提灯を使うことが多いそうです!
- お墓参り:お盆前に家族で墓を掃除し、花や線香を供えます。お盆の最後の日である8月15日の夕方にお墓参りをして、御先祖様の霊をお見送りすることが多いようです。この時間帯にお墓へ行くと多くの方がお参りにいらしゃっています
- 迎え火・送り火:御先祖様の霊が迷わず来て帰ってこれるように焚く火。地域によって材料がおがら、松明など異なります
青森県

最初は北の青森県から!青森県では墓参りの際に花火をする地域もあるそうです。青森で有名な「ねぶた祭り」は2025年は8月2日から8月7日までのお盆前に開催され、お盆前の風物詩となっています。
「ねぶた祭り」はお盆前にあることから、元々は川や海に入って身を清める、また農作業の疲れと眠気を取るところから始まっています。後に自分が水に入る代わりに藁人形や人の形に切り抜いた紙、灯籠を流すようになったといいます。そしてお盆の最終日に御先祖様の霊を送る灯籠流しの風習が合体して、灯籠(ねぶた)を主役とした祭りに発展した。灯籠(ねぶた)が巨大化するにつれて、水に流すことをやめて町の中を曳き回す祭りになったといわれています
東北以外に住んでいたらあまり聞きなじみのない「ねぶた」という響きですが、これは「眠たし」に由来しており、元々の農作業の疲れと眠気を取るところからきています。青森市では「ねぶた」、弘前市では「ねぷた」になるのは方言の違いはないかと言われているそうです
東京都
次は日本の首都である東京です!新暦のお盆である7月13日から7月16日に盆迎え火・送り火を焚くの風習があります。浅草の「ほおずき市」が風物詩として有名ですね!都市部では簡略化される傾向もあるそうです。
浅草のほうずき市とは、毎年7月9日・10日に浅草寺で開催される夏の風物詩です。境内には約100軒もの露店が並び、鮮やかな朱色のほおずき(鬼灯)が吊るされた光景は、訪れる人々の目を楽しませます。この市は、浅草寺の「四万六千日」の縁日と重なり、この日に参拝すれば46,000日分の功徳が得られるとされることから、多くの参拝客で賑わいます。
ほおずきは、魔除けや厄除けの象徴として親しまれ、贈り物やお守りとしても人気があります。江戸時代から続くこの行事は、信仰と季節感が融合した浅草ならではの文化であり、東京の夏を彩る伝統的な祭りのひとつです。
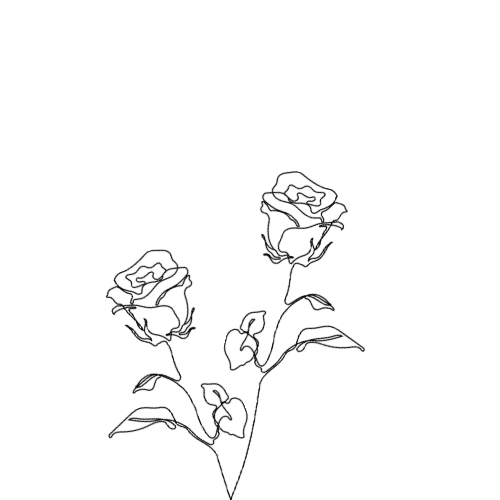
簡略化されているとは悲しいですね…
京都府

次は長年都として栄えた京都府の風習を紹介します。京都の夏の風物詩として知られる「五山の送り火」は、毎年8月16日に行われる伝統行事で、先祖の霊を送るための宗教的儀式に由来しています。中でも「大文字焼き」は最も有名で、東山如意ヶ嶽に「大」の字が炎で浮かび上がる光景は、京都の夜空を荘厳に彩ります。
五山の送り火は、「大文字」「妙法」「舟形」「左大文字」「鳥居形」の五つの火床で構成され、それぞれ異なる山に点火されます。これらの火は、お盆の終わりにあたる日に、迎えた祖霊を再びあの世へ送り返すための「送り火」として焚かれるもので、仏教的な意味合いが強く、地域の信仰と深く結びついています。
「大文字焼き」という呼称は、特に如意ヶ嶽の「大」の字を指すことが多く、観光客にも親しまれていますが、地元では「送り火」としての厳粛な意味が重視されています。火床の準備や点火は、地元の保存会によって代々受け継がれており、火床の位置や薪の組み方などにも細かな伝統が存在するそうです
徳島県
次は四国地方より徳島県の風習をご紹介します。「阿波踊り」が全国的に有名。日程は8月12日から8月15日です。先祖供養の踊りが観光イベントとしても発展。
「阿波踊り」は阿波踊りは、徳島県を代表する伝統的な盆踊りです。「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」という囃子言葉に象徴されるように、観客も踊り手も一体となって楽しむのが魅力です。
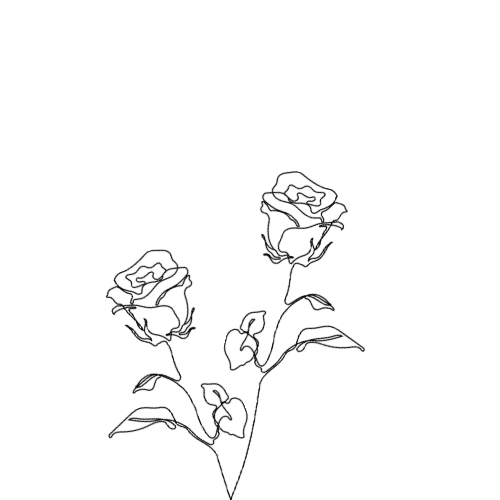
「踊る阿呆に見る阿呆」ってどこか聞き覚えのある歌詞のような…
踊りは「男踊り」と「女踊り」に分かれており、鳴り物には三味線、太鼓、鉦などが使われ、街中に響き渡る音と熱気が祭りを盛り上げます。起源は江戸時代に遡り、庶民の娯楽として発展してきたそうです。現在では国内外に広がり、地域文化の誇りとして受け継がれています
長崎県
次は長崎県です。長崎県では爆竹を鳴らしながら精霊船を曳く「精霊流し」という亡くなった人の霊を送り出すための儀式があります。華やかで賑やかに御先祖様を送るの儀式です!日程は8月15日です!
「精霊流し」とは、遺族が手作りした「精霊船」に故人の名前や遺影を飾り、爆竹を鳴らしながら市内を練り歩き、最終的に船を海や川へ流すものです。派手な装飾や勇壮な音が特徴で、他地域の静かな送り火とは全く異なり、異国情緒ある長崎らしいですよね
沖縄県
最後は沖縄県です!沖縄県ではウンケー(迎え日)、ナカビ(中日)、ウークイ(送り日)と3日間に分かれています。日程は一般的なお盆と違って、旧暦のお盆に当たる7月13日~7月15日にあります。特徴として、エイサー踊りを踊りつつ町を練り歩くというものがあります。
エイサー踊りには「地謡(じうたい)」と呼ばれる歌い手が伴い、独特のリズムと旋律が祭りの雰囲気を盛り上げます。地域ごとに振り付けや衣装が異なり、個性豊かな演舞が見られるのも魅力のひとつのようです。
まとめ
いかがだったでしょうか?お盆にも様々な過ごし方がありますね!みなさんはどうお過ごしでしたか?お盆を機に自分の御先祖様をご自身の御実家の地域のやり方で御先祖様に想いを馳せてみてはいかがでしょうか?





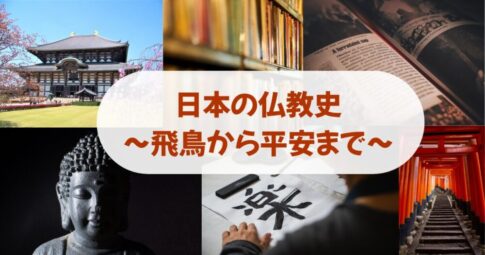
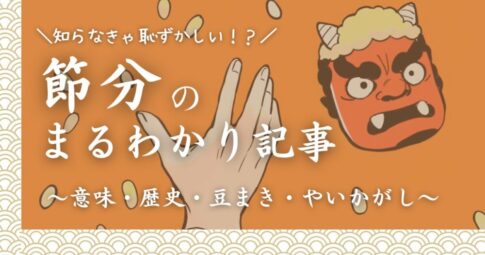






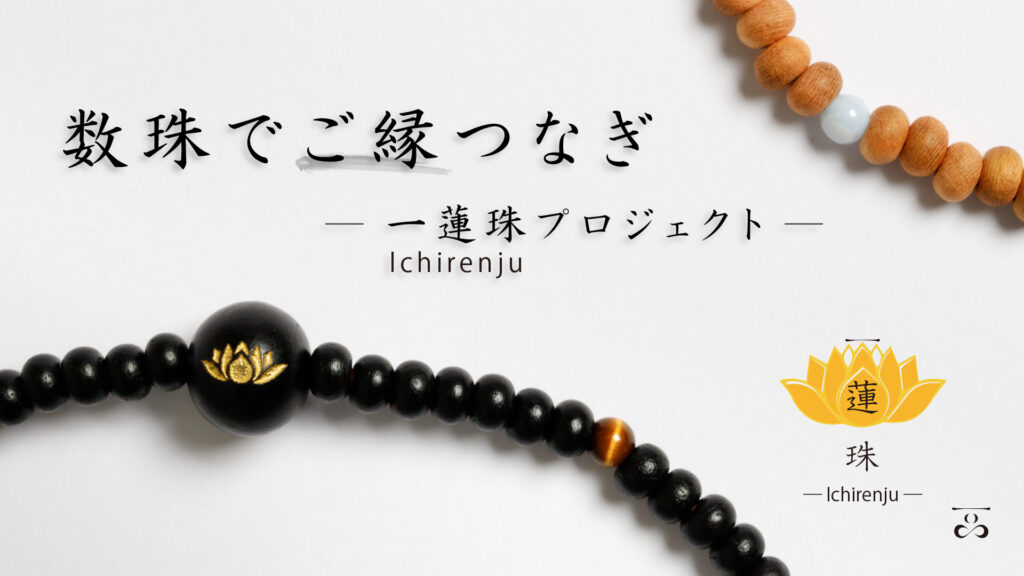


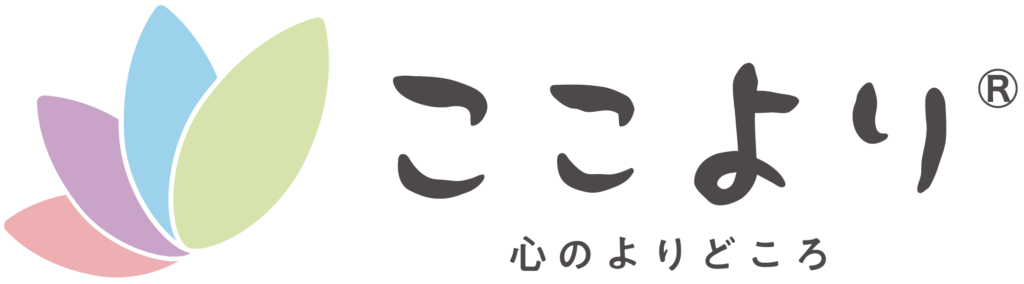
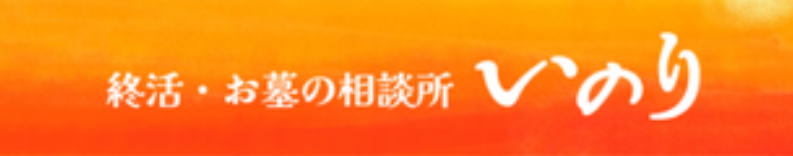


どうも!今年は初盆なのでお盆はお家で過ごすインターン生のけいです!
お盆って川に何かを流す風習があったり、海に入っては行けなかったり、お墓で花火をしたりいろいろな風習がありますよね!
今回はそんな全国の様々な風習を紹介していきます!